
プレイしながら、「こんな世界をどうやって作っているんだろう?
ゲーム業界で求められる人材とは?「開発費高騰」のニュースから自分の「可能性」を考えてみた
こんにちは。在宅時間を楽しく過ごそう、運営者の「O」です。
在宅時間が増えて、じっくりゲームをプレイする機会が多くなりました。最近のゲームって、本当にすごいですよね。グラフィックは実写と見間違うほどですし、ストーリーは深い感動を与えてくれます。プレイしながら、「こんな世界をどうやって作っているんだろう?」と、そのクオリティの高さに圧倒されることもしばしばです。
先日、ふと気になって、最近のゲーム開発費について少し調べてみたんです。すると、AAAタイトルと呼ばれるような大作ゲームだと、開発費だけで100億円超え、なんていう話も珍しくないみたいで…。本当に驚きました。
その大きな理由として、開発スタッフの「人件費」と、ゲームを知ってもらうための「マーケティング費用」が、昔とは比べ物にならないくらい上がっている、ということが分かりました。
その時、私ふと思ったんです。ゲームファンとしては「高くなったなー」「だからソフトの値段も上がるのかな?」で終わってしまう話ですけど、見方をガラッと変えてみると…。
「費用が上がる」ということは、それだけ「専門的なスキルを持つ人」や「ゲームを広める専門家」が業界から強く求められていて、その価値が上がっている、ということですよね。
「私たち(ゲームファン)は、『自分はあくまでプレイする側だ』と思い込んでいないか?」
「『ファンでいること』が一番しっくりくるから、それ以外の可能性が『見えなく』なってしまっていないか?」
そんな、ちょっとした好奇心が湧いてきたんです。
注:この記事は、特定のキャリアや転職を推奨するものでは一切ありません。あくまで私「O」がゲームファンとして、「今、ゲーム業界の裏側ではどんなスキルが求められているんだろう?」という好奇心から調べたことをまとめたものです。でも、この記事を読み終わる頃には、あなたも自分の「隠れた可能性」に気づいて、新しい世界を覗いてみたくなるかもしれませんよ。
私たちが普段遊んでいるあの素晴らしいゲームが、どんな専門家たちの手によって作られ、私たちの元に届けられているのか。その「すごさ」を、少し違った角度から一緒に感じてみませんか?
- ゲーム開発費高騰の背景にある「人材需要」という側面
- ゲーム業界で「作る側」に求められる専門的なスキルとは
- ゲーム業界で「広める側」に求められる重要なスキルとは
- 業界の動向を知ることで、自分の「隠れた可能性」に気づけるか
開発費高騰は「スキルの価値」の表れ?

開発費高騰は「スキルの価値」の表れ?
まず、なぜ「人件費」や「マーケティング費」がこんなに上がっているのか、もう少し掘り下げてみますね。どうやらこれは、単に物価が上がったという単純な話ではなく、ゲーム業界で求められる人材の「専門性」が、昔とは比べ物にならないくらい上がっていることと深く関係しているみたいです。
そもそも、ゲーム産業自体がものすごい勢いで成長している、という大前提があります。例えば、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)の発表によると、世界のゲーム市場規模は今や約30兆円(!)にもなるそうです。30兆円というと、ちょっと想像もつかない規模ですが、日本の国家予算の一般会計歳出が約110兆円ほどですから、その3割近いと考えると、とんでもない巨大産業だということが分かりますよね。
そして、同じくCESAのデータによれば、国内のゲーム産業で働く人の平均年収は、他業界と比較しても高水準(平均708万円)というデータも出ています。(出典:一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会のプレスリリース)
日本の給与所得者全体の平均年収が400万円台半ばであることを考えると、この「708万円」という数字は非常に高い水準です。もちろん、これは平均値なので、全員がこうだというわけではありませんが、業界全体として高い給与水準にあることは間違いなさそうです。
この「年収が高水準」という点こそ、まさに私たちが注目したい「人件費の高騰」=「高度な専門スキルに対する価値の高さ」を示しているんじゃないかな、と私は考察しています。それだけのお金を払ってでも「来てほしい」と思われる高度なスキルを持った人材が、この業界を支えている、ということですね。
私たちはつい、「自分にはそんなスキルはない」と最初から決めつけてしまいがちです。でも、まずは「市場ではこういうスキルが高く評価されているんだ」という事実を、客観的に知ることから始めてみるのはどうでしょう。
高度な技術が求められる開発現場

高度な技術が求められる開発現場
最近のゲーム、特にAAAタイトルと呼ばれる大作は、グラフィックが実写と見間違うほどリアルです。オープンワールドの広大なマップを自由に動き回れたり、キャラクターの表情一つとっても、喜怒哀楽の繊細な感情が伝わってくるようです。光の反射や雨に濡れた地面の表現、風にそよぐ草木一本一本の動きなんかも、現実と見紛うほどです。
昔、例えばスーパーファミコンの頃は、「ドット絵」という限られた色とマス目の中で、いかにキャラクターを魅力的に見せるかという「職人技」が求められていました。それはそれで本当に素晴らしい技術でしたが、今は違います。
3D空間の中で、リアルな人体構造や物理法則に基づいた動き、光の屈折まで計算に入れた描画、それらを同時に処理しなくてはなりません。求められる技術が、根本から変わっているんですね。
こうしたゲームを作るには、当然ながらものすごく高度な技術が必要です。これは家庭用ゲーム機だけの話ではなく、スマホゲームだって例外じゃありません。ひと昔前の家庭用ゲーム機(例えばPS2とかPS3とか)を超えるようなクオリティのものが、今や手のひらの上で動いているわけですから、驚きですよね。
これは、スマホ自体の性能(スペック)が劇的に向上したこともありますが、それ以上に私たちプレイヤーの「目」が肥えてしまったことも大きいかなと思います。「スマホゲームだからこの程度でいいや」という時代は終わり、「スマホでもPCや家庭用ゲーム機並みの体験がしたい」というニーズが高まった結果、開発に求められる技術レベルも上がり続けているんですね。
専門分化するクリエイター
このクオリティを実現するため、開発現場は「専門家集団」になっているようです。昔のゲーム開発では、一人のクリエイターがキャラクターも背景もドット絵も描く…なんてこともあったかもしれませんが、今は違います。
私たちは「ゲーム開発」と一口に言いますが、その中身は驚くほど細分化されています。
例えば「デザイナー」と一口に言っても、昔のように一人が何でもやる、というよりは高度に専門分化しているそうです。
- キャラクターモデラー: 主人公やモンスターの3Dモデルを作る専門家。単に形を作るだけでなく、そのキャラらしさや魅力を立体に落とし込みます。私たちが感情移入するキャラクターの「存在感」は、この方たちの技術にかかっています。
- 背景(エンバイロメント)アーティスト: 美しい景色や建物、ダンジョンなど、ゲームの世界そのものを作る専門家。プレイヤーが「この世界にいたい」「冒険したい」と思える空間をデザインします。「あの絶景、すごかったな」という感動は、まさにこの方たちの仕事ですね。
- モーションデザイナー(アニメーター): キャラクターに「動き」をつけて命を吹き込む専門家。歩き方ひとつ、剣の振り方ひとつで、そのキャラの性格(内気、豪快など)まで表現します。「あのアクション、滑らかで気持ちいい!」と感じるのは、この方たちのおかげです。
- エフェクトアーティスト: 炎、水、光、爆発などの「演出(エフェクト)」を作る専門家。これが派手でカッコイイと、バトルも一気に楽しくなりますよね。必殺技の「ドーン!」という迫力は、エフェクトにかかっています。
- UI/UXデザイナー: メニュー画面やボタン、HPバーなど、プレイヤーが快適に遊ぶための「操作画面(UI)」と「体験(UX)」を設計する専門家。ここが分かりにくいと、どんなに面白いゲームもストレスになってしまいます。私たちが直感的に操作できるのは、この方たちの計算された設計があるからなんですね。
エンジニア(プログラマー)も同様です。「プログラマー」と一括りにされがちですが、実際には非常に細かく役割が分かれています。
エンジニアも細かく専門分化されています。
- グラフィックスエンジニア: 光や影、水の表現など、ゲームの「見た目」の根幹となる描画プログラムを作る専門家。
- AIエンジニア: 敵キャラクターが賢くプレイヤーを追い詰めたり、仲間キャラクターがうまく連携してくれたりする、その「知能」を作る専門家。
- ネットワークエンジニア: 世界中のプレイヤーとオンラインで対戦したり協力したりする際、遅延(ラグ)なく快適に遊べるように通信部分を作る専門家。
- サーバーサイドエンジニア: 特にスマホゲームなどで、プレイヤーのデータ(レベルや所持アイテム)を安全に保存・管理する「裏側」のシステムを作る専門家。
こうした高度な専門スキルを持つ人材の需要が非常に高まっている一方で、そのスキルを持つ人材は世界的に見ても限られている(あるいは育成に時間がかかる)ため、結果として人件費の上昇、つまり「スキルの価値の上昇」につながっている、と私は考察しています。
ゲームを「届ける」専門家の重要性

ゲームを「届ける」専門家の重要性
もう一つの「マーケティング費用」の高騰。これも「人材の需要」と密接に関係がありそうです。
今の時代、どれだけ面白いゲームを作っても、その存在を知ってもらえなければ遊んでもらえません。特にスマホゲームはApp StoreやGoogle Playに、PCゲームはSteam(世界最大のPCゲームプラットフォーム)などに、それこそ毎日のように膨大な数の新作がリリースされています。Steamでは年間1万本以上の新作がリリースされるとも言われており、まさに「情報の洪水」状態です。
この「情報の洪水」の中で、自社のゲームを見つけてもらい、興味を持ってもらい、ダウンロード(購入)してもらう必要があります。
そこで、「どうやってゲームの魅力をターゲットに届けるか」を考える専門家、つまり「マーケター」の役割が非常に重要になっているようです。何十億、何百億もかけて作ったゲームも、知ってもらえなければ開発費を回収できませんから、マーケティングは開発と表裏一体の、極めて重要な役割なんですね。
マーケティングの具体的な役割
昔はテレビCMをバンバン流すのが中心だったかもしれませんが、今はもっと複雑で、専門的です。
- Web広告: YouTubeの動画広告やSNS(X, TikTok, Instagramなど)、Webサイトのバナー広告などを、どの層(年齢、性別、興味など)に、いつ(時間帯)、いくらで出すか、細かく調整・最適化します。
- インフルエンサー施策: 人気のゲーム実況者やVTuberにPR(案件)を依頼します。ただ依頼するだけでなく、そのインフルエンサーのファン層がゲームのターゲットと合っているか、過去に炎上などを起こしていないかなど、緻密な分析とリスク管理が必要です。
- SNS運用: X(旧Twitter)やTikTokなどで公式アカウントを運用し、最新情報を流したり、ファン参加型のキャンペーン(例:「#〇〇の思い出」を投稿しよう)を行ったりして、コミュニティを盛り上げ、話題(バイラル)を作ります。
- データ分析: これが非常に重要です。広告の効果(いくら使って何人インストールしたか=CPA)や、ゲーム内のユーザーの動向(どこで離脱しているか、どのアイテムが売れているか)をデータで分析し、次の施策(広告の改善やゲーム内イベント)を考えます。
こうしたデジタルマーケティングのスキルを持つ人材の需要も、ゲームを「作る」側と同じくらい高まっているんだろうな、と感じます。開発費の高騰は、そのままマーケティング予算の高騰にも直結しているわけですね。
ゲーム業界で「注目されるスキル」を考察
では、具体的にどんなスキルが「需要が高い」あるいは「注目されている」のでしょうか。ここも、繰り返しになりますが、あくまでゲームファンの視点から「こんなスキルがあるんだな」「こういうのが大事なんだろうな」という観点でまとめてみます。
ここからは、少し視点を変えて、「もし自分があの世界に関わるとしたら?」という、ちょっとワクワクする視点で見てみませんか?
「作る側」の技術(開発系)

作る技術
ゲーム開発の現場では、「ゲームエンジン」という開発ツール(ゲームを作るための土台となるソフト)が広く使われているそうです。昔はゲーム会社が自社で専用のエンジン(例えばカプコンの「REエンジン」など)を作ることが多かったようですが、今は高性能な汎用エンジンがあり、これらを使いこなすスキルが、まずベースとして求められるみたいですね。
代表的なゲームエンジン
Unity(ユニティ):
おそらく、今一番広く使われているエンジンの一つじゃないかなと思います。スマホゲームからインディーゲーム、コンシューマーゲーム(任天堂Switchのゲームなど)まで、本当に幅広く使われています。『ウマ娘 プリティーダービー』や『原神』といった大ヒットスマホゲームもこれで開発されているとか。比較的、学習情報がインターネット上に多く、個人でも触れやすいため、インディーゲーム開発者が多いのも特徴かもしれません。プログラミング言語は「C#(シーシャープ)」がメインとのこと。C#はマイクロソフトが開発した言語で、比較的学びやすいとも言われていますね。
Unreal Engine(アンリアルエンジン):
こちらは、とくに大規模で、フォトリアルな超美麗グラフィックのゲーム開発でよく使われる印象です。『ファイナルファンタジーVII リバース』などが有名ですね。こちらは「C++(シープラスプラス)」という言語がメインで、Unityより学習のハードルは高いかもしれませんが、その分できることも多い、というイメージです。また、「ブループリント」という、プログラミングコードを書かずに視覚的にロジックを組める機能もあり、デザイナーさんなどが簡単なギミックを作る際にも使われるそうです。
グラフィックデザインのスキル
こうしたツールを使いこなし、リアルなグラフィックを生み出す3Dデザインのスキルも、非常に専門性が高い分野だなと思います。単に絵が描けるというだけでなく、「Maya(マヤ)」や「Blender(ブレンダー)」といった3D CGソフトを使いこなす技術が必要なんですね。
特に「Blender」は、以前はプロの現場では「Maya」が主流でしたが、近年、無料で使えるにも関わらず非常に高機能であることから急速にユーザーを増やしており、プロの現場での採用例も増えているようです。コミュニティが活発で学習資料が多いのも魅力ですね。
「どうせ専門学校とか行かないと無理でしょ」と、私も思っていました。でも、「Blender」のように無料で始められるプロ用ツールが存在する、という「事実」を知るだけでも、「学習コスト」という参入障壁が、昔よりずっと下がっていることに気づかされます。
「広める側」の技術(企画・マーケ系)

広める側」の技術(企画・マーケ系)
こちらは「届ける」側のスキルです。ゲーム業界というと「作る」側ばかり注目しがちですが、「広める」側も非常に重要なんだな、と今回調べてみて改めて感じました。
そしてここが、今回の考察で私が最も「ハッとした!」と感じたポイントです。
それは、ゲーム開発の専門技術(プログラミングなど)がなくても、「他の業界で培ったスキルが、そのまま“高い価値”として活きる分野」だという点です。
Web・デジタルマーケティングスキル
例えば、あなたが今、ゲームとは全く関係ない業界…そうですね、ECサイト(ネット通販)やWebサービス業界などで働いていて、Web広告の運用経験があるとします。
あるいは、自社のSNSアカウントの運用(中の人)の経験がある、YouTubeやTikTokのトレンド分析が趣味、という方もいるかもしれません。
これまでの私たちは、「それはゲーム業界のスキルではない」と無意識に分類していませんでしたか?
でも、上で見たように、ゲーム業界は今、まさにその「デジタルマーケティング」のスキルを、高い予算を投じてでも必要としています。ECサイトで「CVR(購入率)」をどう上げるか、という知識は、ゲームで「インストール率」をどう上げるか、という課題にそのまま応用できるわけです。
「自分にはゲーム業界で役立つスキルは何もない」という思い込みが、実は「すでに持っている貴重なスキル」の価値を見えなくしていた…なんてことも、あり得るのかもしれません。
コミュニティ運営のスキル
最近は、ゲームをソフトとして「売って終わり」ではなく、発売後もアップデートやイベントで長く遊んでもらうのが主流です(こういうのを「GaaS = Games as a Service」と呼ぶこともあるそうです)。
そのため、X(旧Twitter)やDiscord(チャットツール)、あるいはゲーム専門のSNSなどでファンと積極的に交流し、コミュニティを盛り上げ、ファンの意見(「このキャラが強すぎる」「こういう機能が欲しい」など)を開発チームに正確にフィードバックする「コミュニティマネージャー」という役割も注目されているみたいです。
「ゲームが好き」という熱意に加えて、こうした「広めるスキル」「ファンと繋がるスキル」は、今後ますます価値が高まる分野なのかもしれません。
「未経験」でも関われる分野は?

Screenshot
ここまで聞くと「専門スキルがないと無理なのか…」と思ってしまいますが、「未経験」でも関われる分野はあるのでしょうか。
もちろん、いきなり最前線のエンジニアやデザイナーになるのは非常に難しいと思いますが、開発スキルがなくてもゲームへの情熱を活かせる分野もあるようです。
ただし、先ほども触れたようにゲーム業界は人気がある業界なので、「未経験可」といっても競争率は高いかもしれません。そして何より、「未経験可」=「楽」では全くなく、むしろそこを「新しい世界の入り口」として、夢中になって勉強し、スキルを身につけていく意欲が大切なんだと思います。
未経験から目指しやすいとされる主な職種
あくまで一般論ですが、以下のような職種は比較的入り口として名前が挙ることが多いようです。
| 職種 | 主な仕事内容 | 求められること(私の考察) |
|---|---|---|
| デバッガー(QAテスター) | 発売前のゲームをひたすらプレイし、バグ(不具合)がないかを探すお仕事。 | ゲームの品質を守る「最後の砦」ですね。単に「バグを見つけた」ではなく、「どういう操作をしたらそのバグが100%起きたか」を論理的に説明し、開発者が修正できるように報告する能力(再現性の確保)が非常に重要だそうです。ゲームを「楽しむ」視点ではなく、むしろ「壊そう」とする視点や、忍耐力、集中力、論理的思考力が求められそうです。ここから開発の知識を学び、プランナーなどにステップアップする方もいるとか。 |
| プランナー(アシスタント) | 「どんなゲームが面白いか」「どんなイベントをやるか」を考える企画者の補佐。 | 最初は先輩プランナーの資料作成(ExcelやPowerPointなど)や、ゲーム内のパラメータ(敵の強さなど)のデータ入力・管理といった地道な作業から学ぶことが多いようです。面白いアイデアを出すだけでなく、それを開発チーム全体(エンジニア、デザイナー)に正確に伝えるための資料作成能力や、「この企画は技術的に可能か、予算内で収まるか」を考える論理性、そして何よりチームの橋渡し役としてのコミュニケーション能力が重要になってきそうですね。 |
| カスタマーサポート | プレイヤーからの問い合わせ(「バグじゃないか?」「アイテムが消えた」「操作方法がわからない」など)にメールやチャットで対応するお仕事。 | ゲームへの深い理解はもちろん、プレイヤーの不満や疑問に寄り添う丁寧なコミュニケーション能力が求められます。まさに「会社の顔」とも言える重要な窓口です。そして、ただ対応するだけでなく、プレイヤーから寄せられた「生の声」を集約・分析し、「こういう不満が多い」「こういう機能が望まれている」と開発チームにフィードバックする、重要な役割も担っているそうです。 |
ゲーム業界への関わり方って、私たちが思っている以上に本当に色々あるんだなと感心します。
まとめ:業界の裏側を知ることは、自分の「未来」を知ることかもしれない

業界の裏側を知ることは、自分の「未来」を知ることかもしれない
今回は、ゲーム開発費の高騰という話題から派生して、ゲーム業界で求められる人材やスキルについて、ファン目線で考察してみました。
いやあ、深掘りしてみると、私たちが普段楽しんでいるゲームの裏側には、本当に多様で、高度な専門スキルを持った方々がたくさん関わっているんですね。改めて驚きました。
でも、今回の最大の収穫は、そこではありません。
「業界の裏側を知ること」で、「エンドロールの見方が変わる」…それも、もちろんそうです。ですが、一歩踏み込んで、「自分自身の『思い込み』に気づくきっかけになる」ということでした。
私たちは、ゲームをクリアした時に流れるエンドロール(スタッフの名前が並ぶアレ)を見て、「すごいな」と感動します。でも、その瞬間、「自分はこっち側(見る側)の人間だ」と、無意識に線を引いていないでしょうか?
もし、あのエンドロールに自分の名前があったら…。
自分がデザインしたキャラクターが、世界中のプレイヤーに愛され、生き生きと動き回っているのを見たら…。自分が企画したゲーム内イベントで、SNSが「神イベ!」「楽しすぎる!」と熱狂している反響を、オフィスのモニターでチームのみんなと喜びながら眺めていたら…。
想像するだけで、ちょっと鳥肌が立ちませんか?
「自分には無理だ」といういつもの考えを一度止めて、「もしできるとしたら、どんな関わり方が一番ワクワクするだろう?」と、純粋な好奇心で考えてみる。
その第一歩として、「じゃあ、今、世の中(ゲーム業界)には、具体的にどんな『需要(=求人)』が“実在”しているんだろう?」と、客観的な情報を調べてみるのは、すごくワクワクする在宅時間の使い方だと思いませんか?
「自分には無理だ」と思っていた職種が、実は「未経験可」として募集されていたり、自分の「別の業界のスキル」が、思いがけず「まさに今、求められるスキル」としてリストアップされているのを発見したり…。
そういう「事実」を発見するだけで、昨日まで「見る側」だと思っていた自分が、明日は「作る側」のスタートラインに立っている。そんな可能性を想像すると、在宅時間がもっと楽しくなりませんか?
【本記事のスタンスとご注意】
改めて明記いたしますが、この記事は、私「O」がゲームファンとしての好奇心から市場の動向や関連情報を調べ、個人的な考察をまとめたものです。特定の業界へのキャリア、就職、転職についてアドバイス、推奨、または斡旋することを意図したものでは一切ありません。</YMYL(Your Money Your Life)領域に配慮し、読者様の人生や経済的な選択に影響を与えるような断定的な表現は固く避けております。
もし、ご自身のキャリアや就職・転職について具体的な検討をされる場合は、このようなインターネット上のいち個人の考察を参考にされるのではなく、必ず転職エージェント、キャリアコンサルタント、ハローワークなど、公的または専門的な機関にご相談の上、ご自身の責任において慎重にご判断くださいますよう、強くお願いいたします。




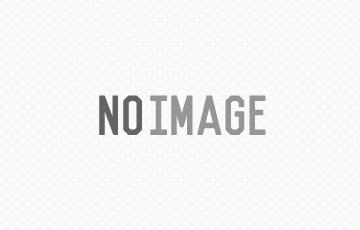











コメントを残す